 |
篆 書
|

甲骨文字(こうこつもじ) 殷後期
殷人は、征戦・狩猟・農耕・出遊など、あらゆることがらについて、神意を問うために占いをしました。
亀甲や牛骨の裏面に溝を彫り、表面に出たひび割れによって占いました。筆画は直線的で字形は簡潔ですが、緊張感のあふれた造形です。 |
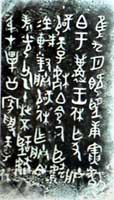
獻殷銘文(けんきめいぶん) 西周初期
殷・周時代の銅器の銘文を金文と呼んでいます。当時の古い書体の呼び名としても使われています。
銘文には獻という人が、主君から青銅の飾りのついた車を賜与されたので、その恩寵にこたえたという事が書かれています。
字形は自然で大小入りまじっていますが、よく形がまとまりがあります。 |
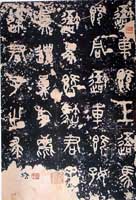
石鼓文(せっこぶん) 東周
金文の次にくる字画文字・篆書の遺品です。
実印の文字がこの範疇に属します。祭祀のため青銅器に鋳込まれた金文に替わり、政治儀礼のために石に刻された文字で、その名の通り鼓型の石に刻されています。
始皇帝時代の小篆の祖とされ、大篆とも呼ばれています。 |
隷 書
|
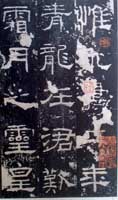
礼器碑(れいきひ) 156年
どこか華やいだ雰囲気をもつ礼器碑は隷書の雄です。横画末尾の波状形を波礫(はたく)と呼び、波礫の美しく伸びた書体を八分体と称します。
篆書の垂直長体に対して、隷書はその文字を周囲に押し広げる文字で、水平の扁平体の姿をしています。 |
草 書
|

木簡(もっかん)
草書は楷書から行書へ、さらに行書をくずして草書が生まれたと考えられやすいのですが、草書は楷書に先行して生まれました。
草書は書簡など書く速度が優先化され、字画を省略した文字です。 |
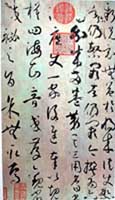
書譜(しょふ) 唐(687)
孫過庭の書譜はすぐれた書の評論であり、また唐代の代表的な草書の名跡です。書者であり著作者でもある孫過庭は、この書譜を書いたことによって、書の歴史にその名を留めました。
学書者の必読の書論であるとともに、草書の手本としては最高のものです。 |
行 書
|

蘭亭序 (らんていじょ) 王義之
蘭亭序は東晋時代に王羲之が曲水の宴を開催し、その日の状況を書いたものとされています。
現存する蘭亭序は唐代になってから太宗皇帝の命を受け、唐代の書人たちが忠実に臨書したものとされています。
蘭亭叙は王義之の行書の代表作で、行書の入門法帖として最適なものとされています。 |

争坐位稿(そうざいこう)674 顔真卿
顔真卿の書簡の原稿です。点画の中へ筆の力を盛りこみ、巻きこむように一気に書き進む書きぶりには、人間の意志というものが強く感じられます。
王義之の書は天地自然と一体となった華やかに対し、顔真卿の書は人間性を発露した逞しい書風を創りだし、後代に与えた影響の面では、王義之を凌ぐほどの地位を確立しました。 |
楷 書
|

雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうのじょ) 653 緒遂良
玄奘三蔵の漢訳仏典の功に、唐の太宗と皇太子(高宗)が与えた序文です。これを緒遂良が書き、陳西省長安の慈恩寺大雁塔にはめこまれました。
緒遂良は欧陽洵、虞世南とともに初唐の三大書家の一人で、とくに楷書に絢爛たる光輝を与えました。軽妙な筆使いは、風に吹かれて天空に舞う花びらのようだと評されています |

九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんのめい)632 欧陽詢
楷法の極則であり、書の中の書です。
主横画は右上がりで主縦画は垂直です。真直ぐに刻されたその姿は、引き締まり緊張感に溢れています。
|

孔子廟堂碑(こうしびょうどうのひ)628〜630 虞世南
長安(西安)の孔子廟再建の記念碑である孔子廟堂碑は、欧陽絢の「九成宮醴泉銘」に比べると、まるで紙に書かれている感じで穏やかな印象です。
その穏やかさが日本人に好まれています。
|
 |
|
|
|